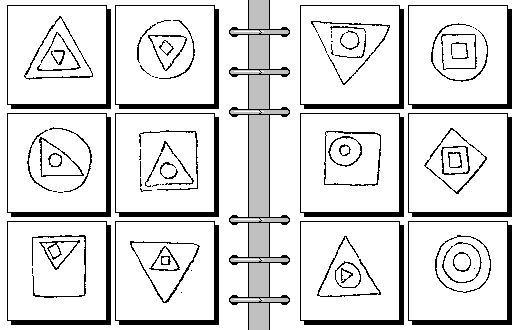人間の思考はシンボルの集まりを再度シンボルとして認識することで進行してゆく。例えば、以下の問題*1を解く場合について例に考える。これは Bongard Problem という有名な問題で、左右6枚の模様はそれぞれ別のルールに従っている。このルールを発見するのがこのパズルの目的である。
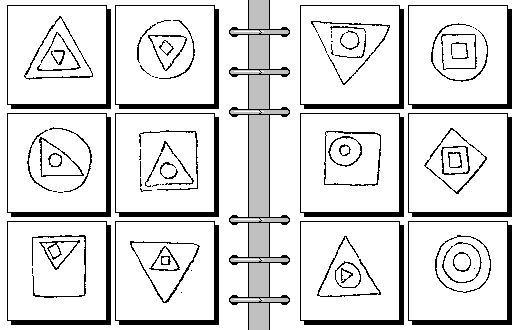
すべての画像は、○△□が入れ子になっている。この入れ子の順序を外側から順に縦に並べて書くと次のようになる。

図示してしまうと瞭然だが、左は真ん中の行がすべて△であるのに対し、右は真ん中の行がすべて△以外の図形である。ここで重要なのは、上のように描かれてしまえば、人はパターンを「一発で」認識できるということである。このように人間がひと目見てそれと認識できるようなパターンをシンボルと呼ぶことにする。△はシンボルであり、△の列もまたシンボルであり、それゆえにわれわれはここにルールを見出すことができている。裏を返せば、「一列に並んだ△」(ないしそれに類する表現)にそれ自体の意味を見出すことができなければ、人は上記の問題を解くことができないということだ。そのような人は「ほら、△が一列に並んでいるだろう」と答えを教えても納得できない。これは単純な例なのでそのような事態は想像しづらいが、もう少し複雑なシンボルになるとそれに対する認知能力を持たない人が案外多くいたりして、不幸な断絶が発生したりする。それはさておき。
文章を書く筋力がめっきり落ちてしまった。それから、言葉とその旋律に対する感受性の鈍麻。労働は悪い。
ここでいうシンボルとはなにか。人間の頭の中に特別の場所を割り当てられているパターンのことだと僕は思っている。人間の頭に入ってくる視覚的聴覚的その他的パターンは無数に存在するが、その中で人間生物の生存に重要なものはそう多くない。そうしたものに特別の符号を割り当て、それ以外を切り捨てる、要は情報の圧縮だけれど、おそらく脳はそれをやっている。その際、類似したパターンには類似の符号が割り当てられるが、この類似性を規定するのは、そのパターンを認知した直後に取るべき行動である。トラに遭遇した場合とクマに遭遇した場合、どちらも取るべき行動は逃げることだが、それゆえにクマとトラには類似の符号が割り当てられるべきなのであり、実際そのようになっているはずである。シンボルは多くの場合に予測に関わるために、シンボルは一部が欠けたとしてもそれが復元できる場合が多い。あるいはそのような復元が可能なパターンを、生き物はシンボルとして獲得している。現在を見れば過去/未来が復元できるという意味で、法則もまたシンボルである。
林檎や樹はシンボルであり、これらの結合すなわち林檎が樹になっているという事態もシンボルであり、それゆえサルは林檎に手を伸ばす。《それ》がシンボルとして分節化されてはじめて生き物は意味のある(という表現の意味がそれなのだが)行動を取ることができる。ここで重要なのは、シンボルの結合が有意味なのは、結合したシンボル集合がまたシンボルである場合に限るということだ。△の並びは、「一列の△」というシンボルを呼び起こして初めて、先の問題の答えを人に教えるのである。
データ分析における可視化というのは、「人間というパターン認識器」が何らかのシンボルを見出だせるようにデータを変形することである。そういう意味で、カーネル法がデータ空間を曲げるのとなんら違いはない。モデルの解釈性云々というのも、そこに人間の知っているシンボルが存在するか否かというだけの話である。
言葉もまたシンボルの一種である。単語はシンボルであり、文もまたシンボルである。言語には、シンボルがまた別のシンボルを誘発するという性質があり、言語的思考はそのようにして進む。誘発されるシンボルに強い制約がかかっている場合に、それは論理的であると呼ばれる。一般に言語的思考は永久に続くものではなく、どこかしらでシンボルがシンボルを誘発しなくなる。それは例えるなら数を繰り返し掛けた結果極端に大きくなったりほぼ0になったりするようなもので、パターンがシンボルとして認知される領域から出ていってしまうのだ。ところでシンボルがシンボルを永久に算出し続ける領域があって、それは数と計算である。そのようなことが可能となるためには、計算におけるシンボルの誘発(変換)には何らかの特殊な性質が要請される(先の掛け算の例えを用いるなら、常に1を掛けているような)はずだ。それがどういうものであるのか興味がある。
人工知能が人間より賢くなって人間に理解を超えた思考をするようになると言われるけれども、ここで人間を超えるのはおそらく認知できるシンボルの複雑さであって、しかし無限の世界を相手取って思考するためにはただ複雑なパターンを認識するだけでは駄目で、やはり何らかの「計算」を生み出す必要があるだろうと思う。それはやはりシンボルに対する変換として何か特殊な性質を持っているはずで、その大雑把な仕組みを理解すること自体は人間にだってある程度可能なのではなかろうか。ニューラルネットの中身は分からなくとも、なにか巨大な行列を掛けているということは分かるわけだし。
支離滅裂な文章になってしまった。いつか書き直す。